

Table of Contents
学校はどこ?
学校の名前のとおりアメリカ式教育です。
ここに2023年〜2025年 約2年半通っている日本人の生徒の宿題をサポートしています。
Grade 8 ~ 10 の生徒さんです。日本でいうと、中学2年から高校1年くらいの学年です。
筆者の背景は?
- 1991年に日本で生まれ育ち
- 小学校から高校まで公立学校で教育
いわゆる一般的な日本の教育をうけてきたので、その視点から教育の違いを比較していきます。
2019年からホーチミンで英語講師をしております。インター受験をする生徒さんの支援を始めたことがきっかけで、入学後も引き続き家庭教師として学習支援をしています。

教科書を使わない学習方法
日本の公立中学では教科書が無料で配布されていますよね。重たい教科書をカバンに詰めて毎日持ち運びしていたのが懐かしいです。
一方、アメリカは教科書がない学校も珍しくないようです。

Google Classroomでスライドを共有
Google Classroom で教材を管理します。
- 先生がスライドや資料を共有したり
- 生徒は宿題を提出したり
単元の内容は、事前にすべてがアップロードされているわけではなく...
なんと、その日の朝に先生が公開することも!予習ができないようになってしまっています。
プリントやオンライン学習(IXL)を活用
プリントを配布して授業中に取り組んだり、宿題になったりする場合もあります。
IXLというアメリカの総合学習プラットフォームも活用されています。
特に数学の宿題は、IXLを使ってオンライン学習をすることが多かったです。
IXL はこちらから確認できます。
課題図書は学校から借りる
授業で使う本(小説など)は、学校から借りる仕組みです。しかし持ち帰りは禁止!
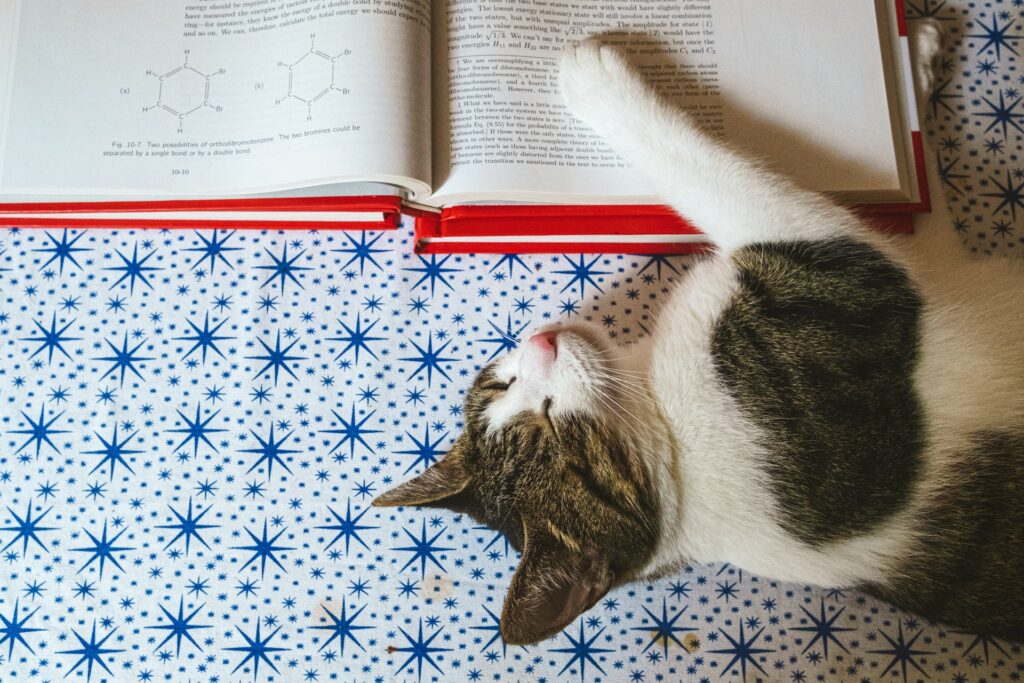
どんな基準に沿ったカリキュラム?
学校によると、
- Common Core を採用している
- NEASC という認証を得ている
正直なところ、Common Core を全部読んで授業内容とちゃんと整合しているかなんて確認できませんよね。
それに、認証機関がどんな基準で認定しているのか も、一般の人にはなかなかわからないものです。

Common Core
コモンコア(Common Core State Standards: CCSS)と呼ばれる全米共通の学習達成基準があります。
日本でいう、文部科学省が定める学習指導要領のようなものです。
NEASC
アメリカには教育認定機関があり、教育機関の質を認証する役割を持っています。
アメリカにある6つの地域認定組織のひとつが、NEASC(ニューイングランド学校大学協会)です。
文部科学省もNEASCの認定校を卒業した人は大学入学資格があると認めています。
保護者がサポートできること
IXL から学習内容を先取りできる
IXLは、アメリカの総合学習プラットフォームです。
Common Core に沿った学年ごとの学習内容を確認・問題演習することができます。
Find your Standards から確認できます。
ネット上で課題書籍を探す
授業で使う本(小説など)は、学校から借りる仕組み、持ち帰りは禁止なので、ネットに頼りました。
幸いにも、すべての課題書籍がネット上で無料で見つけられたので、自宅学習することができました。
さらに、YouTube には朗読動画も見つかりました。聞きながら読むと理解のスピードがあがるので、おすすめの読書方法です。

なぜ教科書を使わない?
①カリキュラムが変わるため
知人のアメリカ人教育者に聞いてみると、
確かに、考えてみると—
💡 新たな発見によって、事実とされるものが変わる
💡 これまでとは異なる視点で物事を考えることが求められる
こうした変化は、教育の世界では十分に起こり得ることですよね。
また、政治的な側面を見ても、教育改革が起こることがあります。
2010年のオバマ政権下で行われた教育改革では、
- アメリカ人全体の教育レベル向上
- 教育格差の解消
を目的に、「Common Core」という新しい教育基準が導入されました。
これは、各州ごとに異なっていた教育カリキュラムを統一しようとする試みでしたが、意外にもまだ導入から15年しか経っていないんですね。
さらに、Common Coreには賛否両論があります。導入時には約45州が参加しましたが、導入から数年後、教育内容に反対する5州ほどが脱退し、州独自の教育基準に戻るという動きもありました。

②思考型の教育なため
特に社会・理科・英語において、
日本の教育は
- 答えが一つ
- 暗記型
の傾向がありますが、
アメリカの教育は
💡 考える力を鍛える
💡 学んだことを文章化する
という特徴があります。
学習ポイントを押さえたら、あとは自分で調べながら課題に取り組むというスタイル。
つまり、教科書から大量の情報を覚えること自体が目的ではないんです。
なので、教科書がなくても教育ができるということだと思いました。

教科書に沿わない柔軟な教育の例
生成AI を使った「新しい技術の」教育
2024年、ChatGPTなどの生成AIが一般にひろまった頃、授業に取り入れられ始めました。
課題の例として
- 長期休暇の思い出をAIでビジュアル化
- 歴史の授業で、AIジャンヌダルクにインタビュー
もちろん、AIの使い方にはルールがあります。
先生がRubric(評価基準)を作成し、ルールに違反すると減点される仕組みです。AIの適切な活用法を学ぶ機会にもなっています。
AIの導入は先生によって差があるものの、学び続ける先生ほど最新技術を授業に活かし、時代に柔軟に対応していると感じました。
YouTube を使った「記憶に残る」教育
理科の授業で、「実験の手順」を学ぶ単元があります。
Imagine → Investigate → Plan → Create → Evaluate
(想像 → 調査 → 計画 → 作成 → 評価)
この流れで実験を進めることを学ぶのですが、課題としてYouTube動画が登場。
「動画のどの部分が、この実験の手順に当てはまるか?」を記述する課題です。
しかも、その動画がとても面白い内容だったので、自然と記憶に残りやすい!
「教材は日常の中にあふれている」ことを実感させる、素晴らしい指導方法だと思いました。

まとめ
インターと日本の学校の違いを「教科書がない」という視点からまとめました。理由を考えてみると、カリキュラムは常に変わるものという価値観や、思考型の教育方法であるという違いをみることができました。
